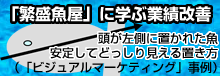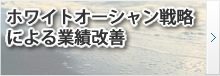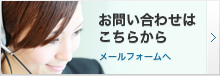「合格歴競争」格差を再生産 難関突破、親の経済力次第: 日本経済新聞
2021年大辞泉が選ぶ新語大賞になった「親ガチャ」。生まれてくる子供は親を選べないことをゲームのガチャに例え、格差が個人の努力だけではくつがえせなくなってきたことを問題視するものです。記事にもあるサンデル教授は「SAT(大学入学統一試験)得点は親の富に比例」とデータを示し、格差是正には社会階層別差別是正措置や適格者のくじ引きによる合否決定等を提言しています。親ガチャはParent Lotteryと訳されますが、その教育面での対策もLotteryでという訳です。問題の所在は、個人の努力では格差をくつがえすことが困難で、さらに世代が進むにしたがってそれが拡大していること。新語大賞にまでなったことは早急な施策が必要なことを物語っています。
⇒ 記事はこちらから
膨張する学習指導要領 理念先行で現場の課題置き去り: 日本経済新聞
米国では、大学入試はSAT、MBA入試はGMAT等、徹底的に基礎力が問われます。そして同試験を経て、論文と面接で応用力が問われます。基礎力が必要条件で応用力が十分条件というのは入学してからも同様。母校のシカゴ大でも、試験では暗記が求められるもの・持ち込み可能なもの等に分かれ、暗記しなければならないものは暗記が求められていました。暗記が全て悪ではないのです。さらに計量経済で有名なシカゴにおいてクオンツを究めているような同級生の大学での専攻は文学・哲学等のリベラルアーツが多いことにも驚きました。「応用力養成の前に(ために)必要なのは基礎力や幅広い教養」なのは日本でも同様のはずではないかと思います。
⇒記事はこちらから
FRB、22年ぶり0.5%利上げ 「量的引き締め」も決定: 日本経済新聞
過度の利上げ懸念後退です。市場では22年ぶり0.5%利上げは織り込み済みの一方、6月利上げ0.75%予想が一時50%となっていたなか、ブルームバーグが前日に「0.75%利上げ巡る質問への回答に注目」との記事を出していたことが象徴するように、6月利上げの水準が市場争点でした。結局、パウエルFRB議長は0.75%利上げを積極的に検討しているものではないとコメント。それを受けて株価3指数は大幅反発、長期金利は下落、ドルも下落、恐怖指数VIXも大きく低下しています。本日以降は、今回の利上げがインフレ抑制に効果をもたらすかどうか、景気後退懸念が顕在化しないかという、より重要な争点に焦点が移ってきます。
⇒記事はこちらから